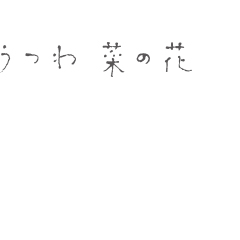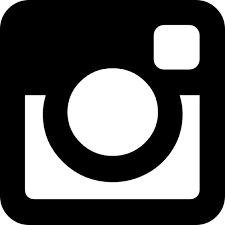小田原のうつわ菜の花を飛び出し、鯉江良二さんと中島勝乃利さん、お二人の作品を新宿の伊勢丹で展示しています。
鯉江さんは、昨年韓国で制作された茶碗を中心に。オリベの壺や、とっくり、ぐいのみなど。
中島さんは、窯から出されたばかりのうつわのほか、高さ1メートルの壺や、陶板などの大きな作品も。
伊勢丹新宿店 本館5Fにてお待ちしております。



17. 2月 2010 by STAFF
Categories: 未分類 |
新宿での二人展が始まりました はコメントを受け付けていません
2010.2/17(水)-23(火)
30年来、おっかけの鯉江さん。
かつて、そのお弟子さんであった中島さん。
やきものの世界を怒涛のようにつきぬけていった
鯉江さんの今回は韓国での仕事。茶碗。
メキシコ帰りの中島さんの織部の食器。
楽しく、多彩でおもしろそうである。
僕自身がほしくなる。
新宿で、お会いしましょう。
菜の花店主 たかはしたいいち。
]
04. 2月 2010 by STAFF
Categories: 未分類 |
伊勢丹新宿店【出店】やきもの・鯉江良二・中島勝乃利 はコメントを受け付けていません
神林さん、安土さんが絵を描き、内田さんが焼いた絵皿二種。
もちろん内田さんが絵を描いたものも。
それぞれに、らしさが出ていて、選ぶ楽しみが。
内田さん制作の鉄枠に木を載せたトレイには神林さんのウサギ。
25. 1月 2010 by STAFF
Categories: 未分類 |
三人展 作品紹介3 はコメントを受け付けていません
神林さんの作品、銅板のゾウとブタ。
安土さんのガラスのトルソ。
安土さんのぽち泡鉢の中には、神林さんの魚がいて、金魚鉢のようです。
21. 1月 2010 by STAFF
Categories: 未分類 |
三人展 作品紹介 2 はコメントを受け付けていません
三人のコラボレーション作品の鳥。
ガラスの頭部を安土さんが、金属の脚を神林さんが作り、内田さんがやきものの胴体でつないでいます。
やきしめのリュトンは、持ち手が三人それぞれの形。
ビールの泡はきめ細かく、熱燗もより美味しく…
20. 1月 2010 by STAFF
Categories: 未分類 |
三人展 作品紹介 はコメントを受け付けていません
2010.1/16(土)-1/25(月)
作家在廊日 16(土)
OPEN 11:00-18:00 定休20日(水)
内田鋼一・神林學・安土忠久がこの夏、この冬と2泊3日の高山合宿をした。
動物をテーマにやきもの、ガラス、彫刻とおのおのの分野。
そしてコラボをおこなった。
原始にもどった感性が生き生き。
となりでは蜂や蝶々が飛び立ち、
リュトンは酒をなみなみつがれるのを待っている。
人は好きな仲間同志、どこでどう出逢うのか。
息が合っているのに群れはなさず。
ただただ黙々とつくり続けるのを見るにつけうらやましい限りである。
ついつい私も引きづられて参入してしまった。
ひきつけられる骨董は古く感じさせずに新しい。
彼らの作品も過去からやってくるように新しい。
小正月すぎに三人が小田原に集まります。ぜひおこし下さい。
2010年正月 菜の花 たかはしたいいち


18. 1月 2010 by STAFF
Categories: 未分類 |
●三人展 内田鋼一/神林學/安土忠久 はコメントを受け付けていません
早川ユミさんの個展は終了いたしました。
最終日の、ちくちくワークショップでは、ユミさんのお話を聞きながら、麻の前かけ作り。
みなさん楽しんでいらっしゃいました。
うつわ菜の花は、新年は1月16日より営業致します。
『安土忠久・内田鋼一・神林學三人展』を予定しております。
2010年も、どうぞよろしくお願い致します。
23. 12月 2009 by STAFF
Categories: 未分類 |
うつわ菜の花営業ご案内 はコメントを受け付けていません
早川ユミのあたたかな衣服展
からだが呼吸するように。
2009.12/12(土)-12/20(日)
作家在廊日 20日(日)
OPEN 11:00-18:00 定休16日(水)
草木染め、手紡ぎ+手織の布たちが旅する手から生まれる。あたたかな、ここちよい、呼吸する衣服となって。ちくちくするときのいつもの音楽はハナレグミと原田郁子ちゃん。
・ゲスト参加/小野セツローさんのスケッチとかんざし
/ちくちくワークショップ
12月20日(日)/1回目:PM1時〜/2回目:PM4時〜
参加費:3500円
ちくちく手縫いでまえかけをつくります。
「にぎりばさみ」だけ持ってきてください。
お申し込み、お問い合わせは
うつわ菜の花0465-24-7020(各回15名)
● 種まきノート(早川ユミ著)アノニマスタジオ刊 発売中
ちくちく、畑、ごはんの暮らしが綴られています。
ぜひ読んでください。
● 早川ユミさんのHP une-une.com
ユミさんのかなでる高知の谷相の
生活の香りと風がまちどおしい。
店主 たかはしたいいち

03. 12月 2009 by STAFF
Categories: 未分類 |
●早川ユミのあたたかな衣服展 はコメントを受け付けていません
伊集院真理子さんの個展は終了しました。
次回は企画展は、12月12日より、早川ユミさんです。
写真は伊集院真理子展です
03. 12月 2009 by STAFF
Categories: 未分類 |
クローズのお知らせ はコメントを受け付けていません
OPEN 11:00 ー 18:00 定休11月25日(水)(最終日29日は17:00まで)
先日、北九州 小倉の「鮨 小山」さんが小田原に来られた。
鮨をいただいた翌日は、伊豆の友人宅に場所を移し、鱧しゃぶ。しめに出された、出し汁で炊いたご飯は、すべての味わいを頂くような美味しさだった。
そんな時、ここにあったらなと思うのは、伊集院さんの土鍋。彼女の土鍋で出しを取ると、「あく」があまり出ない。きれいに透き通った味わい深いおいしい出しがとれるだけでなく、美味しいご飯と「お焦げ」が頂ける。何度もおかわりしたくなる。より一層、美味しさを引き出してくれたに違いない。残念至極。
この冬に向けて土鍋は欠かせない。家族の団欒、友人達と囲んでの食事。同じ釜の飯をいただいている実感がうれしくなる季節です。
伊集院さんのプラチナの皿や急須も加わってモダンな料理がはじまる。
2009年11月6日
菜の花店主 たかはしたいいち

16. 11月 2009 by STAFF
Categories: 未分類 |
伊集院真理子 土鍋とうつわ はコメントを受け付けていません
← Older posts
Newer posts →